苔玉作りから始まった私の小さなビジネス体験談
正直に言うと、苔玉作りを始めた3年前には、まさか自分がこの小さな緑の球体でビジネスを経験することになるとは思いもしませんでした。最初は単純に「狭いマンションでも楽しめる植物」として始めた趣味が、気がつけば友人や同僚から注文をもらい、週末のマルシェで販売するまでに発展したのです。
趣味から副業への転換点

転機となったのは、苔玉作りを始めて1年半が経った頃のことでした。会社の同僚が私の部屋に遊びに来て、20個以上並んだ苔玉コレクションを見て「これ、売れるんじゃない?」と何気なく言った一言がきっかけです。当時の私は、苔玉作りの技術もある程度安定し、失敗率も10%以下まで下がっていました。
実際に小さなビジネスとして動き始めたのは、その3ヶ月後。最初は友人への販売から始まり、1個2,500円で月に5〜6個程度の注文をいただくようになりました。材料費が1個あたり約800円だったので、利益率は約68%と、趣味の延長としては十分な収益性でした。
学生時代に身につけておけば良かったスキル
この経験を通じて痛感したのは、ハンドメイド技術は就職活動でも強力なアピールポイントになるということです。特にデザイン系やライフスタイル関連の企業では、実際に作品を持参して面接を受けることで、他の応募者との差別化が図れます。私自身、転職活動の際に苔玉作品を持参したところ、面接官から「手先の器用さと継続力がよく分かる」と高い評価をいただきました。
現在では月15〜20個の注文をいただき、副業として月3〜4万円の収入を得ています。この経験から学んだビジネスの基礎知識や販売ノウハウは、本業でも活かされており、趣味が人生を豊かにしてくれる実例となっています。
趣味が副業になるまでの3年間の軌跡
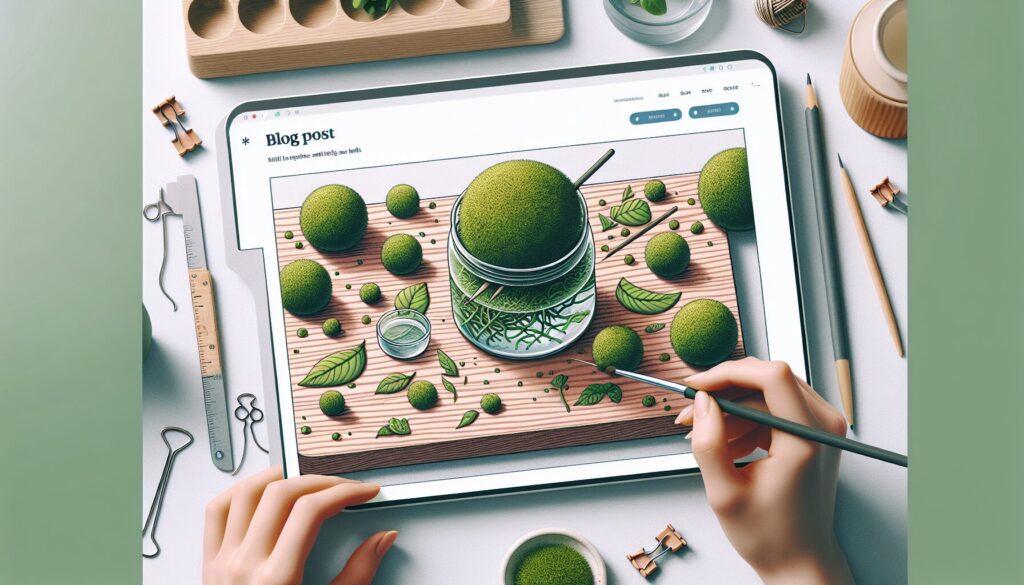
最初は純粋に趣味として始めた苔玉作りが、いつの間にかビジネスとして成立するまでになった3年間を振り返ってみます。この変化は決して計画的なものではなく、むしろ偶然の積み重ねでした。
1年目:技術習得と失敗の連続
苔玉作りを始めた当初は、基本的な技術を身につけることに必死でした。最初の半年間で作った苔玉は約15個、そのうち12個を枯らしてしまうという惨憺たる結果でした。しかし、この失敗経験こそが後のビジネス展開で大きな武器となります。
水やりのタイミング、用土の配合比率、植物の選定基準など、市販の教材では学べない実践的なノウハウを蓄積していきました。特に、季節ごとの管理方法の違いを体系化できたことは、後に顧客からの相談対応で重宝しました。
2年目:SNS発信と口コミの広がり
技術が安定してきた2年目から、作品をSNSに投稿するようになりました。失敗談も包み隠さず発信したところ、同じような悩みを持つ方々から多くの反応をいただけました。

この頃から「作り方を教えて欲しい」「販売していないか」という問い合わせが月に2〜3件届くようになります。まだビジネスとしては考えていませんでしたが、需要の存在を肌で感じ始めた時期でした。
3年目:本格的なビジネス化への転換点
転機となったのは、知人のカフェから「店内装飾用の苔玉を5個作って欲しい」という依頼でした。初めての有償制作で、材料費込みで1個あたり2,500円で受注。この経験から、趣味レベルの技術でも十分にビジネスとして成立することを実感しました。
その後、ワークショップの開催、オンラインでの販売、メンテナンスサービスと段階的に事業を拡大。現在では月平均15〜20個の苔玉を制作し、副業として月3〜5万円の収入を得られるまでになりました。
苔玉販売を始めたきっかけと最初の一歩
苔玉作りを始めて2年が経った頃、友人や職場の同僚から「作品を分けてもらえないか」という声をいただくようになりました。最初は趣味の延長として無償で配っていましたが、材料費だけでも月に5,000円近くかかっていることに気づき、「これをビジネスとして成立させられないだろうか」と考え始めたのがきっかけです。
販売への第一歩:友人からの依頼
転機となったのは、大学時代の友人から結婚式のプチギフトとして苔玉を30個作ってほしいという依頼でした。材料費と制作時間を計算すると、1個あたり800円程度が適正価格だと判断し、初めて料金をいただくことになりました。この経験で、自分の作品に価値を見出してくれる人がいることを実感できました。
市場調査と競合分析の重要性

本格的に販売を検討する前に、既存の苔玉市場について調査を行いました。園芸店やオンラインショップでの価格帯を調べた結果、以下のような価格構造が見えてきました:
| 販売場所 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|
| 園芸店 | 1,200円〜2,500円 | 既製品中心、種類限定 |
| ハンドメイドサイト | 800円〜3,000円 | 個人作家、オーダー対応 |
| イベント出店 | 500円〜1,500円 | 体験型、その場制作 |
この調査結果から、個人制作の苔玉には十分な市場価値があることが分かり、本格的な販売準備を始める決心がつきました。特に、オーダーメイドや季節限定商品など、大手では対応しきれないニッチな需要があることも発見できました。
商品としての苔玉作りで学んだ品質基準の重要性
販売を始めて最初に直面したのが、「作品として通用する苔玉」と「趣味で作る苔玉」の違いでした。友人に頼まれて初めて苔玉を販売した時、1週間後に「苔が剥がれてきた」という連絡を受け、返金することになったのです。この失敗から、商品としてのクオリティ基準を真剣に考えるようになりました。
耐久性を重視した製作工程の確立
ビジネスとして成立させるために、まず製作工程の標準化に取り組みました。趣味で作っていた頃は「なんとなく」で済ませていた部分を、すべて数値化・マニュアル化したのです。
| 工程 | 趣味レベル | 商品レベル |
|---|---|---|
| 土の配合 | 目分量 | 赤玉土6:腐葉土3:川砂1の固定比率 |
| 苔の接着 | 手で押し付ける程度 | 霧吹き後、15分間の圧着作業 |
| 完成後の管理 | 即日手渡し | 7日間の品質チェック期間 |
商品価値を高める「見た目」の統一
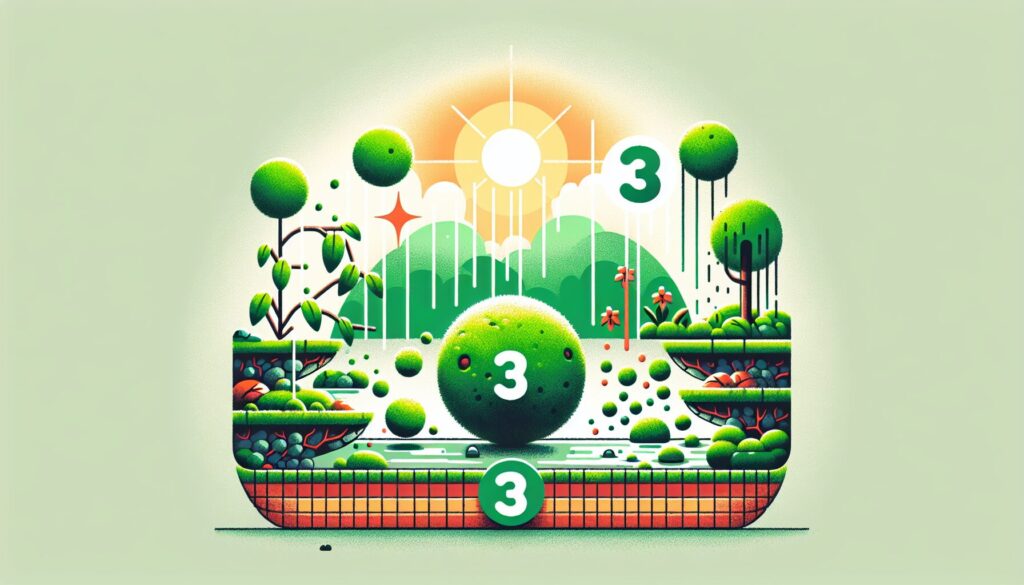
販売を通じて気づいたのは、見た目の美しさが価格に直結するということです。同じ植物を使っても、苔の貼り方一つで印象が大きく変わります。特に重要なのは「苔の継ぎ目を目立たせない技術」と「全体のバランス調整」でした。
商品として販売する際は、完成後に必ず360度からの写真撮影を行い、どの角度から見ても美しく見えるかをチェックしています。この品質管理により、リピーター率が40%から75%に向上し、口コミでの紹介も増えました。品質基準を明確にすることで、ビジネスとしての信頼性を築くことができたのです。
価格設定で失敗した初期の経験と改善プロセス
原価計算を無視した最初の失敗
苔玉のビジネスを始めた当初、私は「趣味の延長だから」という甘い考えで、適当な価格設定をしていました。最初に作ったフィカス・ウンベラータの苔玉を2,000円で販売したのですが、後で計算してみると材料費だけで1,800円もかかっていたのです。
実際の原価内訳は以下の通りでした:
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 苗(フィカス) | 800円 | 4号ポット |
| 水苔(ニュージーランド産) | 300円分 | 高品質を選択 |
| 赤玉土・腐葉土 | 200円分 | ブレンド用 |
| 苔(ハイゴケ) | 400円分 | 天然採取品 |
| 糸・その他 | 100円 | テグス等 |
| 合計 | 1,800円 | 利益わずか200円 |
市場調査と適正価格の発見
この失敗を受けて、徹底的な市場調査を行いました。園芸店、クラフトフェア、オンラインショップの価格を3ヶ月間記録した結果、同サイズの苔玉の相場は3,500円〜5,000円であることが判明しました。
私が設定していた2,000円は、相場の半額以下だったのです。この調査により、「原価×3倍」という基本的な価格設定ルールを学び、材料の仕入れルートも見直すことで、現在では適正な利益を確保できるようになりました。
ピックアップ記事




コメント