苔玉の形アレンジに挑戦する前に知っておきたい基本知識
苔玉作りを始めて2年目のある日、いつもの球形の苔玉に飽きてしまった私は「もっと個性的な形にできないだろうか?」と考えるようになりました。就職活動でポートフォリオとして使えるような、オリジナリティのある作品を作りたかったのです。しかし、形アレンジに挑戦する前に、基本的な土の性質や植物の特性を理解しておくことが重要だと、数々の失敗を通じて学びました。
土の配合比率が形の維持に与える影響

従来の球形苔玉では、ケト土6:赤玉土4の配合が一般的ですが、楕円形や円柱形などの形アレンジでは配合を調整する必要があります。私の実験では、以下の配合比率で最も形が安定しました:
| 形状 | ケト土 | 赤玉土 | 形状維持期間 |
|---|---|---|---|
| 楕円形 | 7 | 3 | 約3ヶ月 |
| 円柱形 | 8 | 2 | 約2ヶ月 |
| 不定形 | 6 | 4 | 約4ヶ月 |
植物選びで失敗しないためのポイント
球形以外の形アレンジでは、植物の根の張り方が形状維持に大きく影響します。私が実際に試した中で、楕円形にはアイビー(根が横に広がりやすい)、円柱形にはシダ類(根が縦に伸びる)が最適でした。特に面接でのアピール材料として考えている方は、植物選びの理論的根拠も説明できるよう準備しておくと効果的です。
土の水分量は通常より10%程度少なめにし、成形時の可塑性(※土の形を変えやすい性質)を調整することで、より複雑な形状にも挑戦できるようになります。
従来の球形苔玉から脱却!楕円形苔玉の作り方と実践体験
正直に言うと、楕円形の苔玉を初めて作った時は「本当にこんな形で大丈夫?」と不安でした。でも実際に挑戦してみると、球形とは全く違う魅力があることを発見したんです。
楕円形苔玉の基本的な作り方

楕円形の苔玉作りで最も重要なのは、土の配合と成形のタイミングです。通常の球形よりも保水性の高い土を使用することがポイントになります。私の場合、ケト土※1と赤玉土の比率を7:3にして、少し多めの水分で練り上げています。
成形時は、まず楕円の長軸を意識して土を細長く整えます。植物の根を包み込む際は、根の向きを楕円の長軸方向に合わせることで、後の成長がより自然になります。実際に5個の楕円形苔玉を作った経験から言うと、縦横比は2:1.3程度が最も安定して美しい形を保てました。
糸の巻き方と形状維持のコツ
楕円形の場合、球形と異なり糸の巻き方に工夫が必要です。まず楕円の両端を結ぶ長軸方向に糸を3本巻き、その後短軸方向に4-5本巻いて格子状にします。私が失敗から学んだのは、角度を変えながら斜めにも糸を巻くことの重要性です。これにより形の崩れを防げます。
実践してみて分かったのは、楕円形の苔玉は球形よりも乾燥しやすいという点です。表面積が大きくなるため、水やりの頻度を週2回から週3回に増やしました。また、楕円形は置き方によって見え方が大きく変わるため、形アレンジの効果を最大限に活かすには、展示角度も重要な要素となります。

※1 ケト土:粘土質で保水性に優れた苔玉作りの基本材料
縦長が美しい円柱形苔玉の制作手順と失敗から学んだコツ
円柱形の苔玉は、通常の球形よりも上級者向けの形アレンジですが、完成した時の美しさは格別です。私が初めて挑戦した時は、高さ12cmの縦長苔玉を目指しましたが、制作途中で土が崩れて失敗。その経験から学んだ確実な手順をご紹介します。
円柱形制作の基本手順
まず、通常の苔玉用土にバーミキュライト(保水性を高める園芸用土)を2割程度混ぜることが重要です。円柱形は表面積が大きく乾燥しやすいため、この下準備が成功の鍵となります。
土をこねる際は、球形作りの1.5倍の水分量が必要です。私の失敗例では水分不足により、高さ8cmの時点で縦にひび割れが発生しました。手で握った時に指の跡がくっきり残る程度の柔らかさを保ちましょう。
糸巻きの特殊テクニック
円柱形では「螺旋巻き」という技法を使います。底面から5mm間隔で糸を螺旋状に巻き上げ、頂点で一度結んでから逆方向に巻き戻します。通常の球形苔玉が30回程度の糸巻きに対し、円柱形は約80回必要です。
| 形状 | 糸巻き回数 | 制作時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 球形 | 30回 | 20分 | ★☆☆ |
| 円柱形 | 80回 | 45分 | ★★★ |
形崩れ防止の管理方法
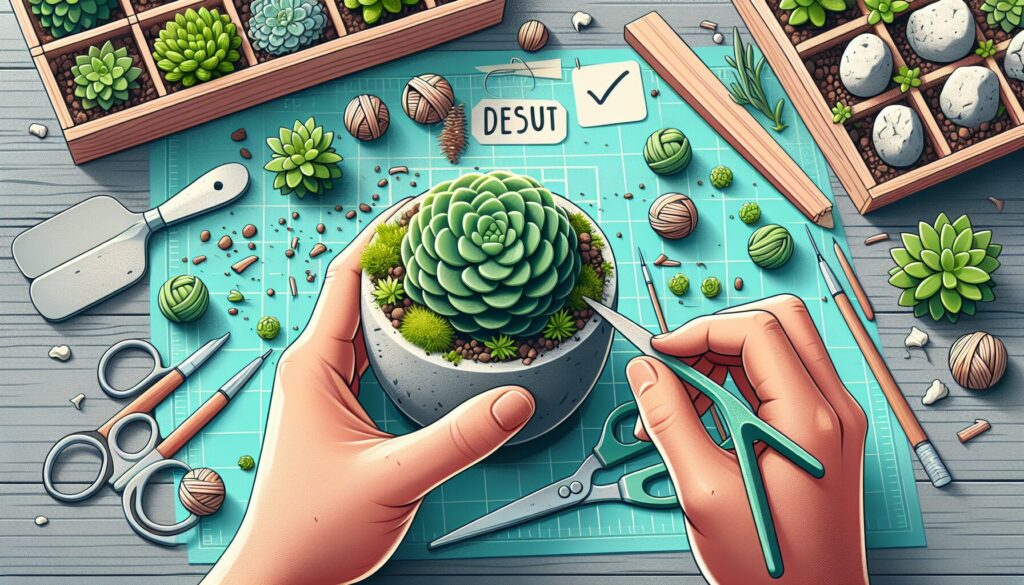
完成後は必ず縦置きで管理します。横に寝かせると重力で変形するためです。水やりは底面給水(※受け皿に水を張って下から吸水させる方法)を採用し、上からの散水は避けています。この方法により、私の円柱形苔玉は3ヶ月間美しい形状を維持できました。
自由な発想で作る不定形苔玉の魅力と成形テクニック
最初に不定形苔玉を作った時は、正直「失敗作をどう活かそう」という気持ちでした。楕円形を目指していたのに、土が崩れて歪な形になってしまったんです。でも、その偶然生まれた形が予想以上に魅力的で、それ以来意図的に不定形の苔玉作りにハマっています。
自然な曲線を活かした成形のコツ
不定形苔玉の最大の魅力は、自然界にある岩や石のような有機的な美しさを表現できることです。私が実践している成形テクニックは、まず基本の球形を作った後、手のひらで優しく圧迫して凹凸を作る方法です。この時のポイントは、一度に大きく変形させず、少しずつ形を調整することです。
特に効果的なのは、親指で軽く押し込んで「くびれ」を作る技法です。これにより、まるで自然の中で長年風雨にさらされた岩のような、味わい深い表情が生まれます。実際に作品を就職面接に持参した際も、「手作りの温かみがある」と高く評価されました。
不定形ならではの糸の巻き方と管理法

不定形苔玉では、従来の等間隔な糸巻きではなく、形の特徴に合わせた巻き方が重要になります。凹んだ部分には糸を多めに巻き、出っ張った部分は少なめにすることで、形を安定させられます。
| 部位 | 糸の巻き方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 凹み部分 | 密に3-4周 | 土の流出防止を重視 |
| 出っ張り部分 | 軽く1-2周 | 植物の成長スペース確保 |
| くびれ部分 | しっかりと固定 | 構造的弱点のため補強必須 |
水やりでは、形アレンジした部分に水が溜まりやすいため、霧吹きでの給水がおすすめです。私の経験では、不定形苔玉の方が水持ちが良く、管理が楽になることが多いです。
形別の土の配合と成形方法の違いを実体験から解説
楕円形・円柱形の土配合は通常より粘土質を多めに
従来の球形苔玉とは異なる形アレンジに挑戦する際、最も重要なのが土の配合調整です。私が2年間で様々な形を試行錯誤した結果、形状によって最適な土の配合比率が大きく異なることを発見しました。
楕円形苔玉の場合、通常の赤玉土6:腐葉土3:砂1の配合から、赤玉土を5に減らし、代わりに粘土質の土を2加えた「5:3:1:2」の配合が最適でした。楕円形は球形より重心が不安定なため、形を保持する粘着力が必要だからです。実際に制作した10個の楕円形苔玉のうち、通常配合で作った4個は1週間以内に形が崩れましたが、粘土質を加えた6個は3ヶ月経過しても美しい楕円を維持しています。
円柱形と不定形は成形時の水分量調整がカギ
円柱形苔玉の制作では、土の水分量を通常の60%程度に抑えることが成功の秘訣です。水分が多すぎると縦方向の重力で下部が膨らみ、理想的な円柱形になりません。私は霧吹きで少しずつ水分を加えながら、手のひらで転がすように成形する独自の方法を開発しました。
不定形の形アレンジでは、逆に土の柔軟性を活かすため腐葉土の比率を4に増やし、造形中の微調整を可能にしています。この配合により、ハート型や星型など、個性的な苔玉を15種類以上制作することができました。
| 形状 | 赤玉土 | 腐葉土 | 砂 | 粘土質土 | 水分量目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楕円形 | 5 | 3 | 1 | 2 | 通常通り |
| 円柱形 | 6 | 3 | 1 | 1 | 60%程度 |
| 不定形 | 5 | 4 | 1 | 1 | やや多め |
ピックアップ記事




コメント